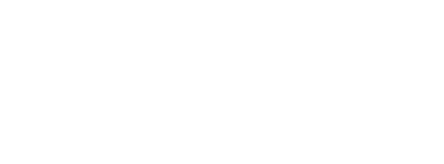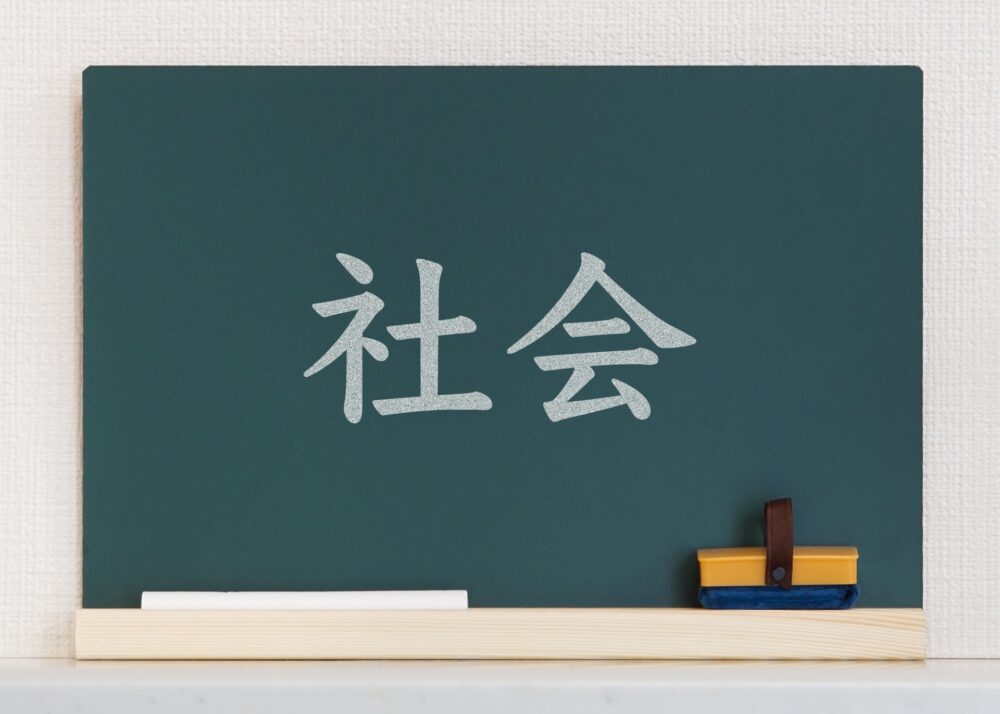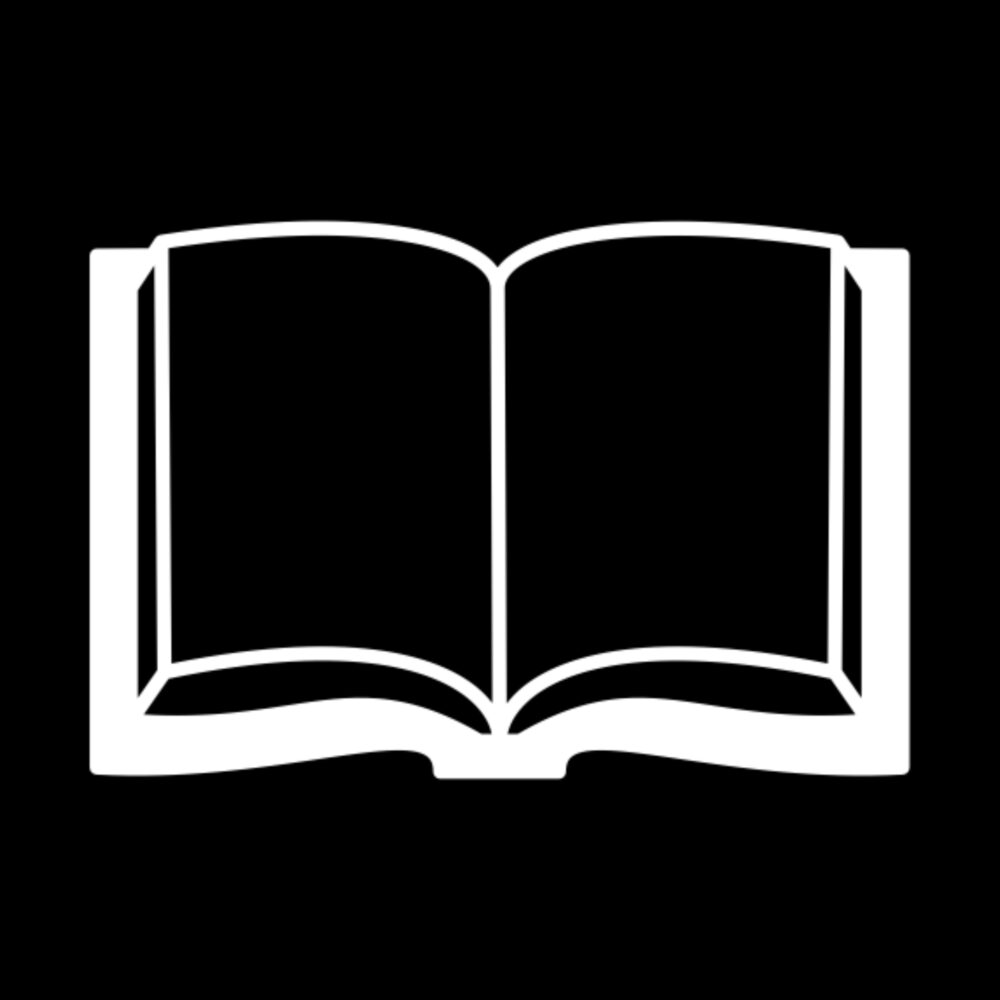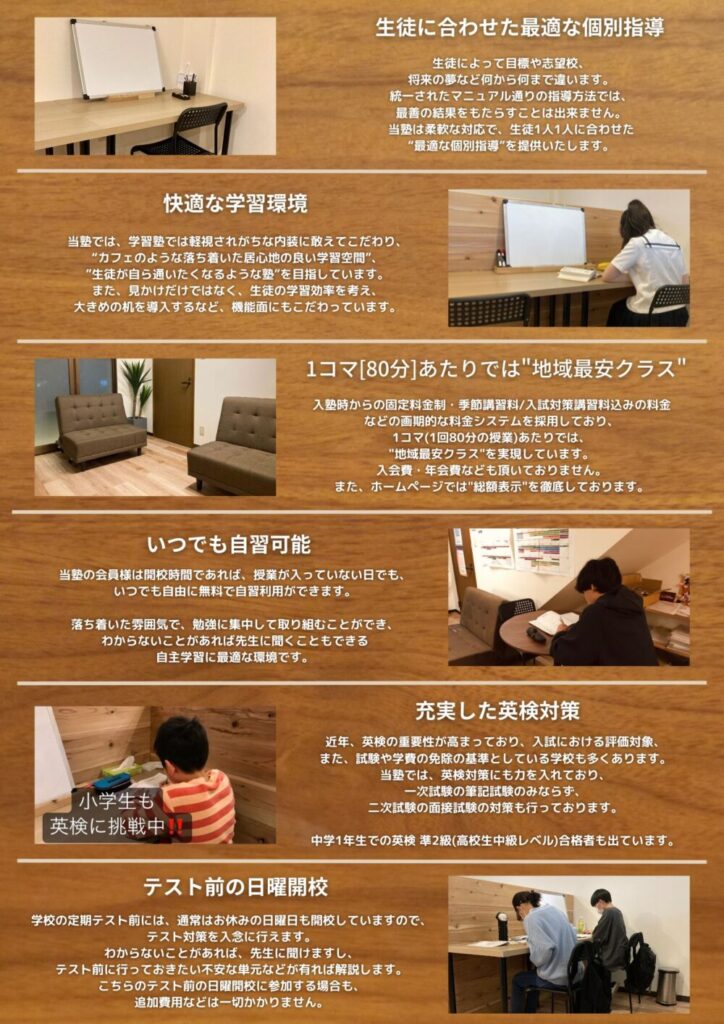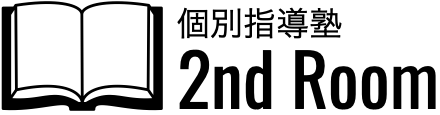さて、前回の記事で予告していた通り、今回は私の得意教科でもある社会の勉強方法について書いていきたいと思います。
私は、中学・高校の社会(高校では世界史,日本史)で学年1位を何度か取っていました。
中学のとき、同じクラスに5教科合計点が学年1位で、のちに大阪大学[日本でトップクラスの大学]に現役合格する凄まじく優秀な同級生がいました。
彼にもなんとか社会単体では勝ってました。
(5教科合計では到底及ばなかった。。。苦笑)
なので、暗記科目に関しては非常に自信あります。
安心して下記の勉強方法を実践してもらいたいです。
社会を勉強する際の大まかな流れ
①問題集(ワーク)
↓
②教科書/授業ノート
↓
③資料集
社会で勉強する際に用いる教材の順番というより、優先順位になります。
とにかく、問題集[ワーク]を解くことが最優先です。
正直言って問題集を完璧にするだけで、最低でも70点くらいは取れるのではないかと思います。
つまり、①の問題集[ワーク]だけで大半の勉強は終了します。
① 問題集[ワーク]編
まずは、問題集から取り掛かりましょう。
基本的には、学校で配布されているワークを行えばOKです。
また、あれもこれも参考書や問題集に手を出す必要はありません。
一冊を完璧に極めれば、定期テストで高得点は取れます。
STEP.1 ワーク[問題集]の答えをノートに丸写しする
※ 私は普段覚える勉強をする際に、一切書いたりはしないのですが、学校に提出しなければならないから仕方なく書いていただけで、どうせ書かなければならないなら有効活用しようということで、この勉強方法を思いつきました。
ここで大切なのは、”必ず問題をしっかり読んでから、覚える意識を持って、ノートに答えを書き写す“ということです。
このとき、「こう聞かれたら、こう返せばいいのか」と覚えながら、“なるべく綺麗な字”で、“正しい漢字”で書いてください。
なるべく綺麗な字で、正しい漢字で書く理由は、このノートに書き写した答えを次も使うからです。
『え、いきなり答えを丸写し!?』
と驚かれる方も多いでしょうが、
塾でも、このブログでも何度も言っていますが、答えを見ることは決して悪いことではありません。
私の経験上、勉強ができる人ほど答えを見ていて、勉強ができない人を答えを見ていません。



ワーク[問題集]が全問正解のまま提出すると学校の先生に丸写ししただけと疑われるかもしれませんが、それはテストの点数が低い人が答えをただ丸写していることが問題なだけで、その後のテストで高得点さえ取れば、たとえワーク[問題集]が全問正解でも信憑性や説得力があるので、全く問題ありません。
実際、私もワーク[問題集]は答えを丸写ししてたので、全問正解のまま先生に提出していましたが、しっかり点数を取っていたので、先生から何も言われたことはありません。
テストの点数が低い人のワーク[問題集]が全問正解だったら不自然ですが、高得点の人が全問正解でも何も不自然ではありません。
つまり、たとえ答えを丸写ししてようが、テストで結果さえ出せば何も言われないし、問題はないということです。
時折、答えのわからない問題を『教科書で調べる』みたいなことをしている子がいますが、
勉強方法として非常に効率が悪いので、やめましょう。
答えを見れば一瞬で解決するのに、教科書でパラパラとページをめくって、どこに書いてあるかもわからない答えを探すなんて作業は、時間がかかるだけで、メリットがないからです。
それは『覚える作業』ではなく、『答えを探す作業』です。
点数を取るために必要なのは、前者の『覚える作業』です。
それに、“教科書のページをパラパラとめくって答えを探す時間”は、勉強時間ではないです。
ただ手と目を動かしてる時間に過ぎません。
STEP.2 ワーク[問題集]を解く
解くといっても、書かなくて大丈夫です。
STEP.1でノートに書き写した答えを下敷きなど(答えを隠せれば何でも良いです。)で隠します。
↓
ワークの問題を読んで答えを考える或いは思い出します。
↓
答えを隠した下敷きなどをスライドさせて、答えが正しかったか確認します。
↓
間違った問題や思い出せなかったワークの問題番号に☑️[チェックマーク]をつけます。
下敷きをスライドさせるだけで、答えが確認できるので、書くと言う行為を省略し、労力を削減できるうえ、時間効率を上げられます。
STEP.3 ☑️[チェックマーク]のついている問題だけを解く
2周目では、1周目で間違った問題、つまり、☑️[チェックマーク]のついている問題のみ行います。
(1周目で解いて正解できた問題は覚えている可能性が高いので飛ばしてOKです。)
解き方は、STEP.2の方法で行ったのと同様です。
答えを隠して、問題を読んで、答えを考えたり思い出して、最後に考えた答えが正しいか確認します。
2周目でも間違ったものには、問題番号のところに☑️[チェックマーク]をさらに追加してください。
間違った数だけ☑️[チェックマーク]がついているような状態になります。
これをすることによって、自分の解ける問題と、解けない問題(苦手な問題)が可視化されます。
STEP.4 全問正解できるまで☑️[チェックマーク]の付いている問題に取り組む
☑️[チェックマーク]の付いている問題が全問正解できるまで、何周もしてください。
何度も行ううちに問題と答えがセットで覚えられていきます。
社会は、問題と答えが入れ替わることも多いので、問題も含めて覚えることが大切です。
1600年に関ヶ原の戦いに勝利し、1603年に江戸幕府を開いた人物は誰か?
→ 徳川家康
徳川家康が勝利した1600年に起きた戦いは?
→ 関ヶ原の戦い
関ヶ原の戦いが起きたのは何年か?
→ 1600年
1600年に関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康が、1603年に開いたものは何か?
→ 江戸幕府
1600年に関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康が江戸幕府を開いたのは何年か?
→ 1603年
これらは一例ではありますが、このように社会はいくらでも、問題と答えを入れ替えたりすることができるので、どこを聞かれても答えられるように、それを想定して問題と答えセットで、しっかり覚えておきましょう。
ワークを全問正解できる状態になるまで、取り組みましょう。
ワークを全問正解できる状態になるまでが理想なので、何周行ったからOKとかではないですが、私はテスト範囲を最低でも3周~5周はしてました。
② 教科書/授業ノート編
教科書か授業ノートどちらが優先かはテストの作成者による
基本的に、学年にその教科の担当の先生が数人いて、交代制でテストを作成していると思いますが、普段授業を担当してくれている先生がテスト作成をしている回は、かなりチャンスです。
テストは、多かれ少なかれ作成者の思想が反映されています。
思想というと大袈裟かもしれませんが、テストの作成者である先生が重要視していることはテストに出される可能性が非常に高いです。
学校の先生が重要視していることは必ず授業中にノートに書かせているはずです。
なので、教科書よりも授業ノートの優先順位を上げて、勉強してください。
教科書や授業ノートは形式上、暗記には向かない
極端なことを言うと、問題集[ワーク]を全問正解できるまで、教科書や授業ノートに手を出す必要はないのではないかと思います。
なぜなら、教科書や授業ノートは形式上、暗記には向かないからです。
ワークは基本的に1問1答の問題形式ですが、それに対して、教科書は基本的に文章形式で書かれています。
文章を読んで、覚えるというのは難易度が高いです。
また、授業ノートとは学校の授業の内容をまとめたノートですが、これも文章形式ではないにしろ、暗記には不向きです。
以前の記事↓でもアクティヴ・リコールの話をしましたが、思い出す作業こそが記憶の定着には最適です。
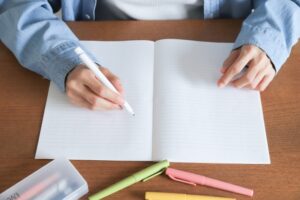
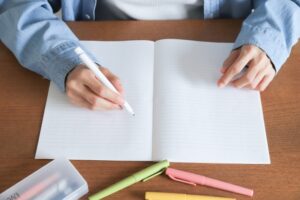
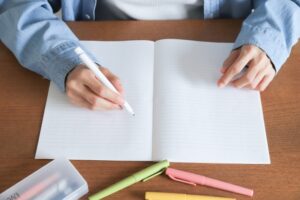
したがって、1問1答の問題形式であるワークを解く際には、答えを思い出すという作業が必要になりますが、 文章形式の教科書や授業ノートを読むことは、その作業がしづらいのです。
まずは『キーワード』を覚えよう
最初にワークをすべき理由は、人物名、出来事名など『キーワード』を覚えるためです。
その『キーワード』すら覚えていないのに、文章を読んでも内容がなかなか理解できないと思います。
英語で例えるなら、英単語を全然覚えてもないのに、長文読解をしようとしているようなものだからです。
ですので、教科書は問題集[ワーク]を全問正解できるほど知識を身につけてから、読んでみてください。
文章の解像度がグッと上がり、より深く理解できるようになると思います。
③ 資料集問題
いよいよ、最終段階です。
資料集で対策するのは、その名の通り、資料問題です。
ただ正直言って、資料集はテスト直前に見るくらいでいいと思います。
なぜ、資料集を用いた勉強が優先順位が低いかという言うと、問題集[ワーク]にも資料問題も含まれていますし、教科書にもある程度は掲載されているからです。
そこから溢れた資料を拾っていく形になるので、資料集は問題集や教科書での勉強を充分行ったうえで、余裕がある人が手を出すくらいのものとして認識してもらって良いと思います。
資料問題は恐らくそれほど多くない。
これは、あくまで定期テストにおける話ですが、それは出題される資料問題の分量です。
定期テストの範囲では、使用できる資料の数自体に限りがありますし、定期テストのほとんどが資料問題ということは非常に稀です。
それに、テスト範囲の資料問題だと、なかなか問題自体にバリエーションが作れないため、同一の問題になりやすい傾向にあります。
(また、作成者である先生の立場を考えると、作成の手間もかかるというのもあると思います。笑)
まとめ
今回は、『定期テストの社会』に特化した勉強方法の紹介でしたが、他の教科に応用することも可能です。
とにかく回数と効率化を重視しただけであり、あまり高度なことをしているわけではないので、再現性は高い勉強方法だと思います。
次回は、反対にNGな勉強方法を紹介したいと思います。